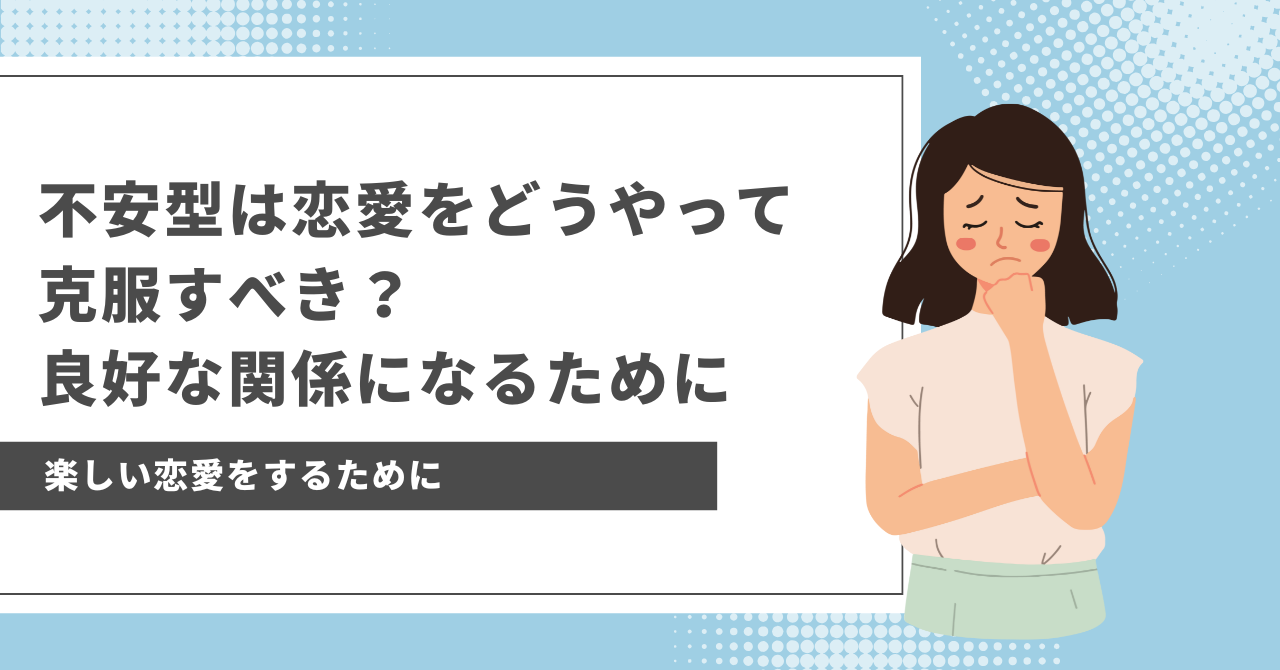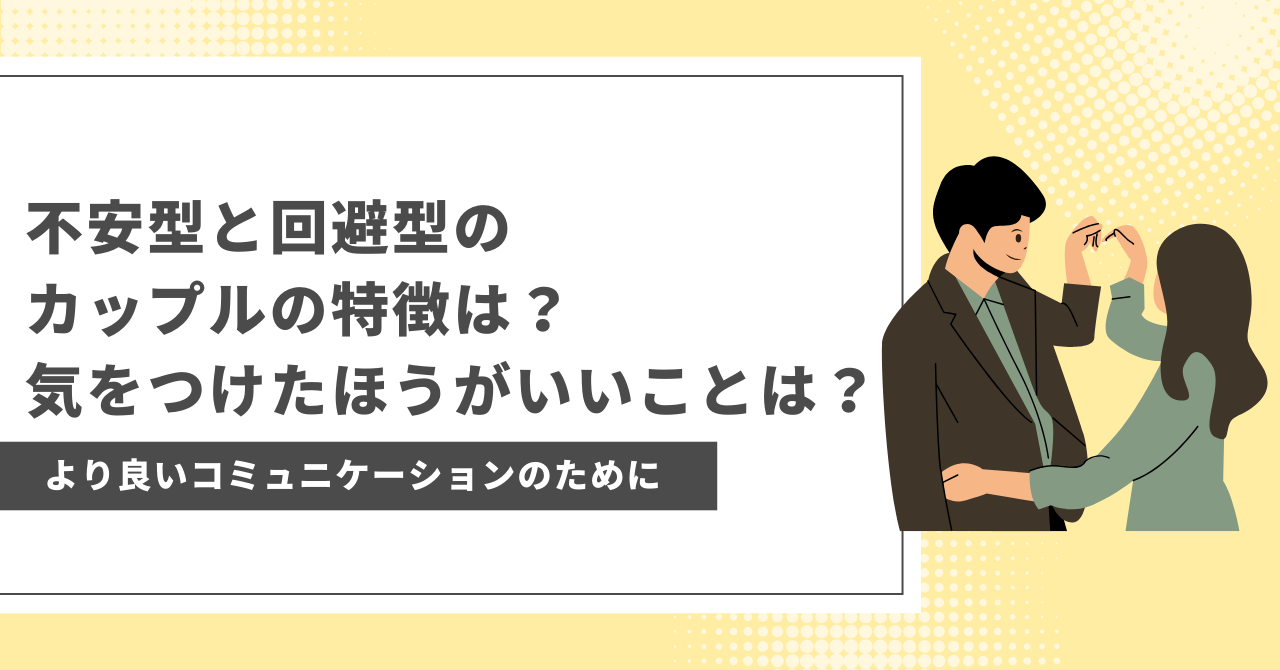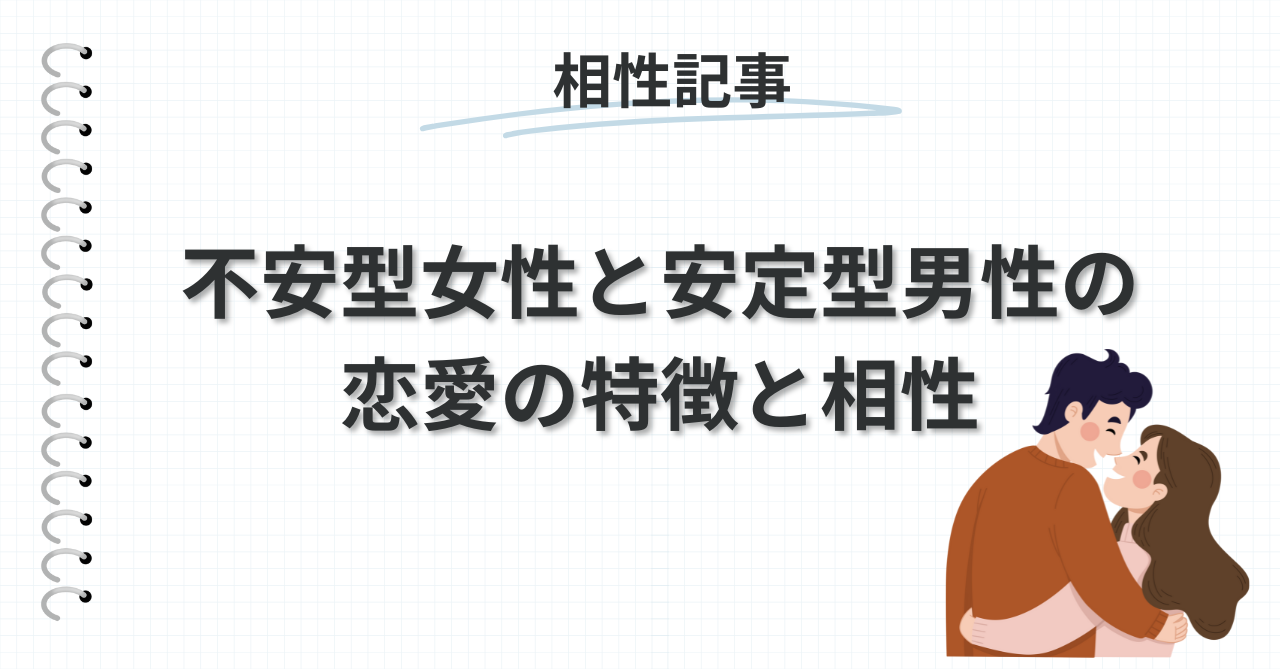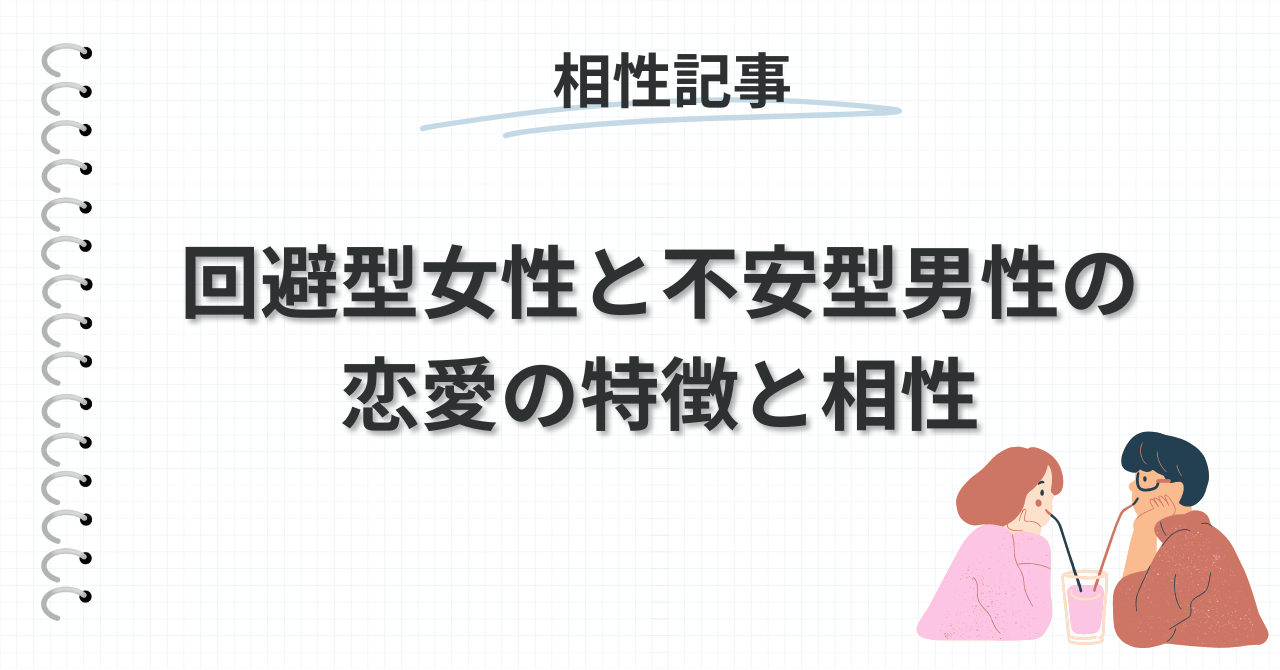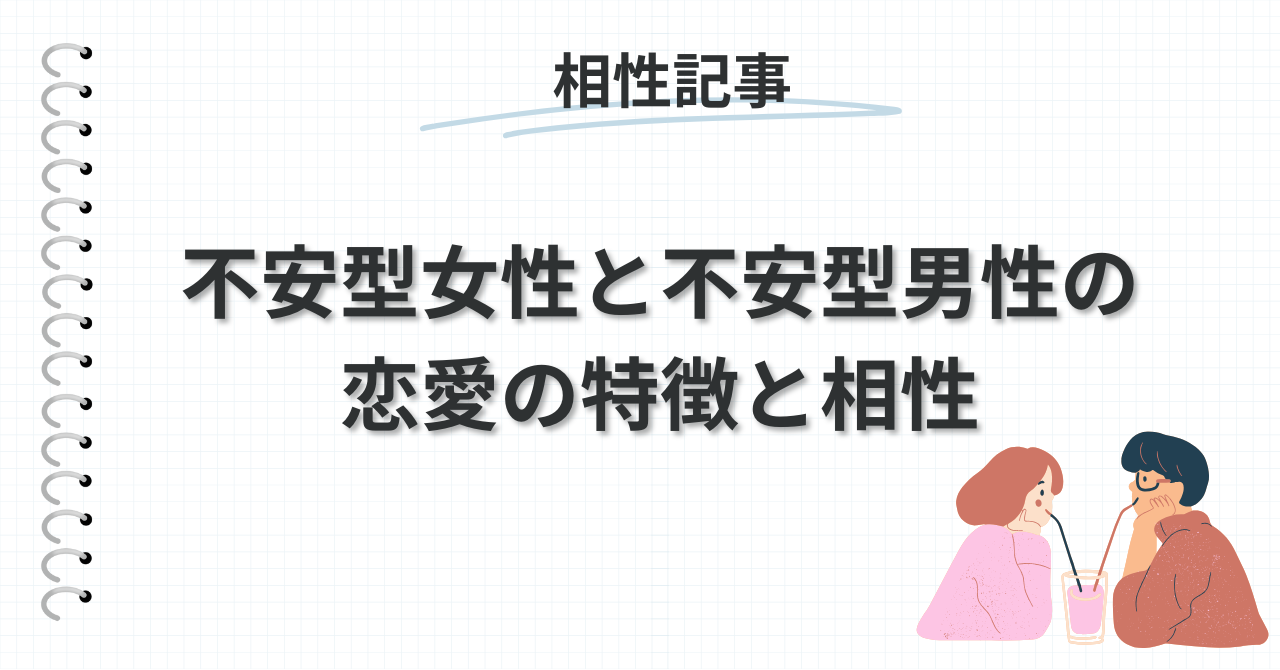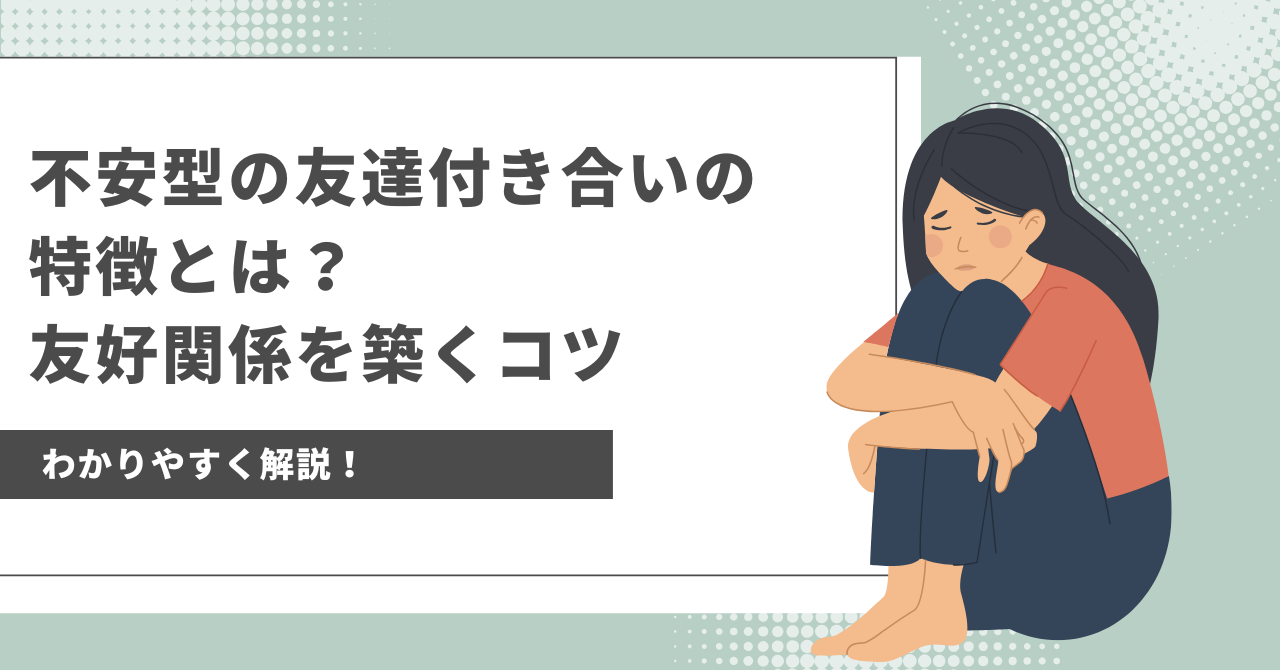不安型×回避型のハイブリットタイプ「恐れ回避型」とは
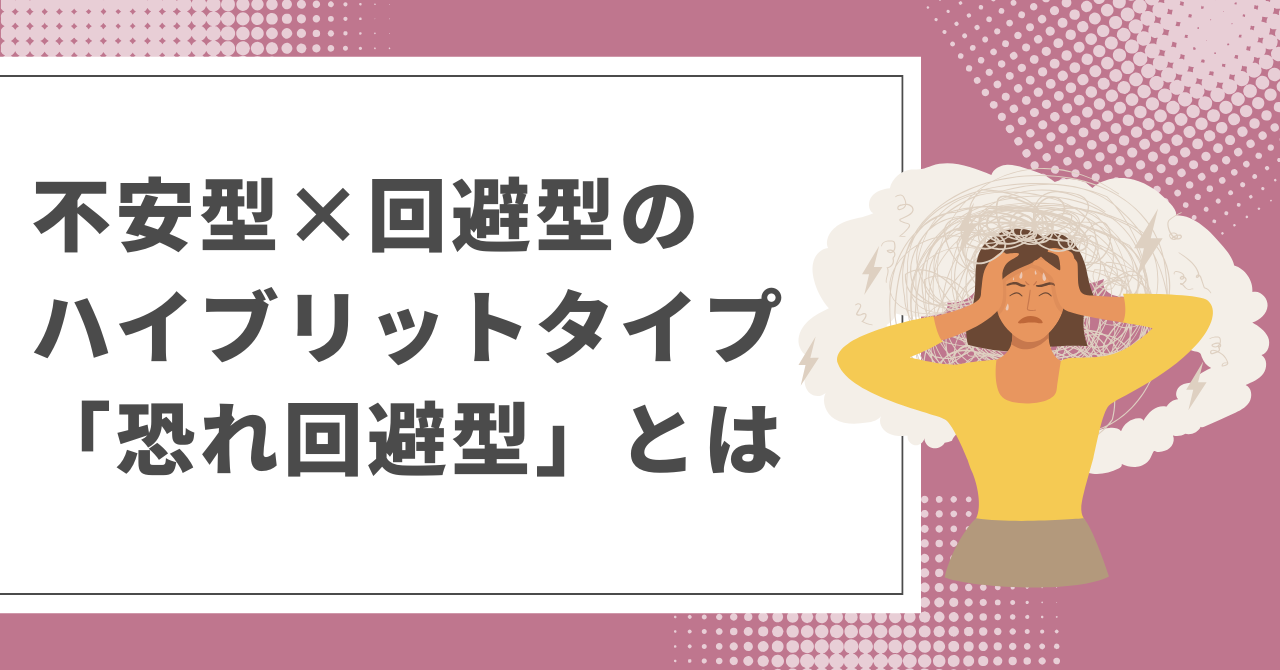
人との距離を縮めたいけれど、実際に近づこうとすると怖くなって逃げてしまう……。そんな相反する気持ちを同時に抱える「恐れ回避型」は、いま注目されている愛着スタイルの一つです。不安型と回避型の両方の要素をあわせ持つため、日常生活や人間関係で大きな困難を感じることが少なくありません。この記事では、恐れ回避型の特徴や原因、対処法などをわかりやすく解説していきます。
恐れ回避型って何?まずは愛着理論をおさらい

愛着理論と愛着スタイル
愛着理論では、人が幼少期に養育者(親など)との間で結ぶ感情的な絆が、その後の対人関係に大きな影響を与えると考えられています。これを「愛着スタイル(愛着タイプ)」と呼び、大まかに以下のような分類がされることが多いです。
- 安全型(安定型)
他者を基本的に信頼し、自分も愛される価値があると感じやすいタイプ。人間関係を築きやすく、適度な自己肯定感を持ちやすい。 - 不安型(不安定型)
「見捨てられるのではないか」という強い恐れや不安を持ちやすく、相手に対する依存や執着が強くなるタイプ。 - 回避型(拒絶型)
深く関わりすぎることを苦手とし、他人との距離を置くことで自分を守ろうとするタイプ。感情を表に出すのが苦手。 - 恐れ回避型
不安型と回避型の両方の特徴をあわせ持つ複雑なタイプ。人とのつながりを強く求める一方で、相手を恐れたり自分が傷つくことを避けようとしたりするあまり、不安定になりがち。
今回取り上げる「恐れ回避型」は、ここに挙げた4番目に当たります。自分でも「なぜこんなふうに感じてしまうのだろう?」と混乱するほど、相反する感情を同時に抱えるのが特徴です。
恐れ回避型の主な特徴

1. 親密さへの強いあこがれと恐怖心が同居
不安型のように「相手と深くつながりたい」「見捨てられたくない」という欲求が強い一方で、回避型のように「親密になりすぎるのは怖い」と感じてしまいます。そのため、近づきたいけど、近づくと怖いというジレンマを常に抱えることになります。
2. 強い不安感と自己否定
「どうせ私は愛されない」「相手を信じたら裏切られるかもしれない」といった思い込みが強く、自分の価値を低く見積もりがちです。それでも他人の存在が気になり、「自分がどう思われているのか」を過剰に気にするため、常に心が落ち着きにくい状態になります。
3. 親密な関係での混乱や衝突
恋人や家族など、本来近い距離感にある相手と関わるほど、不安と回避の両方が顔を出します。たとえば、ある時は相手を強く求めるのに、別の時には過度に距離を置こうとしてしまうといった行動を繰り返し、本人も「どうしてこんな言動をしてしまうんだろう」と戸惑うことが多いです。
4. 試し行動や意地悪な態度
「どうせ自分なんか」と思いながらも相手を失いたくない気持ちがあり、相手がどの程度自分を受け止めてくれるのかを確認するために、試し行動やわざと冷たい言葉をかけるなどの行動をとることがあります。これは「本当に見捨てないでくれる?」という不安感の裏返しと言えます。
恐れ回避型が形成される背景

1. 幼少期の養育環境
恐れ回避型の愛着スタイルが生まれる大きな要因のひとつが、幼少期の不安定な養育環境です。親からの愛情が一貫して与えられなかったり、過度に支配的または放任的な態度をとられたりすると、子どもは「親(養育者)は怖いけれど、いなくなるのはもっと不安」という複雑な感情を抱きやすくなります。
- 無視された経験
肉体的・精神的な愛情不足、放置などによって、「親は怖い存在だが離れるともっと怖い」という矛盾が潜在的に刷り込まれます。 - 一貫性のない対応
ある時は優しく、ある時は厳しく、と極端に振り回されると、「安心して甘えていいのかわからない」という混乱が深まり、子どもは自分の本音や感情を抑えてしまいやすくなります。
2. トラウマ体験
大切な人との別れや、いじめ、災害などのトラウマ体験が、愛着の形成に影響することがあります。もともとの愛着スタイルに加えて、トラウマが引き金となり「恐れ回避」の側面が強まるケースもあるのです。
3. 遺伝的・気質的要因
愛着スタイルは環境的な要因だけでなく、気質や遺伝的要素とも関連しているとされています。もともと不安になりやすい気質や、感情を抑え込みやすい性格の人は、幼少期の環境が重なることで恐れ回避型へと発展しやすい可能性があります。
恐れ回避型が抱える生きづらさ

1. 親密な関係が長続きしにくい
パートナーとの間で、求めすぎる時と避ける時が極端に入れ替わるため、相手を混乱させたり、自分自身も振り回されたりしがちです。それが原因となり、恋愛関係がうまくいかずに別れてしまう、あるいは相手とのコミュニケーションがいつまでたっても安定しないなどの問題を引き起こします。
2. 自己肯定感の低さ
「本当は愛されたいのに、きっと愛されない」「近づいたら傷つくに違いない」というネガティブ思考が強まると、自己否定感がより深まります。自分のどこかで「こんな自分はダメだ」と思い込んでいるため、自信が持てずに苦しんでしまうのです。
3. 人間関係の安定が難しい
職場や友人付き合いでも、人と適度な距離を保つのが難しいと感じる場面が多くなるかもしれません。こちらから近づいておきながら、相手が応じると急に怖くなって引いてしまうなどのパターンを繰り返してしまうと、周囲との信頼関係を築くのに時間がかかります。
恐れ回避型とうまく付き合う・付き合っていくために

1. 自分の愛着スタイルを理解する
まずは「自分がどのような愛着パターンを持っているのか」を知ることが大切です。心理テストやカウンセリング、専門書などを参考にすることで、自分の思考・行動パターンが「恐れ回避型」に近いのかどうかを客観的に把握できます。
2. 一人で頑張りすぎない
恐れ回避型の人は、周囲からのサポートを素直に求めるのが苦手な場合があります。しかし、信頼できる友人や家族、あるいはパートナーに心の内を少しずつ打ち明けることで、「自分の悩みをわかってもらえた」という安心感を得られるかもしれません。多少勇気は要りますが、思い切って言葉にしてみることも大切です。
3. メンタルケアの習慣を取り入れる
日常生活のなかで、次のようなことを意識してみると、不安感のコントロールが多少楽になることがあります。
- 瞑想や呼吸法
深呼吸をしながら自分の身体の感覚に意識を向けると、心が少し落ち着きやすくなります。 - 運動習慣
軽いストレッチやウォーキングでもOK。体を動かすことでストレスホルモンが減り、不安の軽減や気分のリフレッシュが期待できます。 - 日記やジャーナリング
その日あった出来事や自分の感情を文字に起こすことで、「こういうときに恐れと回避の感情が出てくる」というパターンに気づきやすくなります。
4. パートナーや周囲の理解を得る
恐れ回避型の人と親密な関係にある相手(恋人や家族)にとっては「なぜ近づいてきたのに、急に突き放すの?」と混乱することが多いでしょう。そのため、少しでも「こういう理由で混乱している」「近づきたい気持ちもあるけれど、不安でいっぱいになることがある」と説明できると、お互いの誤解を減らすことにつながります。
まとめ
恐れ回避型愛着障がいは、不安型と回避型の両方の特徴が同時に表れるため、本人にとっても周囲にとっても「なぜそうなるの?」と理解が難しい側面があります。しかし、その背景には幼少期の体験やトラウマ、不安定な愛着環境などが深く関わっていることも多く、一概に「わがまま」「面倒くさい」と片付けられない繊細さが潜んでいるのです。
- 「本当は近づきたいけれど、傷つくのが怖い」
- 「人とのつながりに飢えているのに、あえて距離を置いてしまう」
- 「心を開きたいけど、拒絶されるのが不安で開けない」
こんな葛藤を抱えながら、どうにか前に進もうともがいている――それが恐れ回避型の人の現実かもしれません。まずは自分が「そういう心のしくみを持っている」ことを理解し、周りの大切な人にも少しずつ理解してもらうことで、関係の築き方が変わってくる可能性があります。
「恐れ回避型だからダメだ」ではなく、「恐れ回避型としての自分のペースや気持ちを尊重しながら、少しずつ新しいコミュニケーションに挑戦してみる」。その積み重ねが、いつかあなたや周りの人との関係を、より豊かで安定したものへと変えていくきっかけになるかもしれません。焦らず、自分を大切にしながら、一歩ずつ進んでいきましょう。